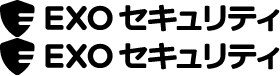
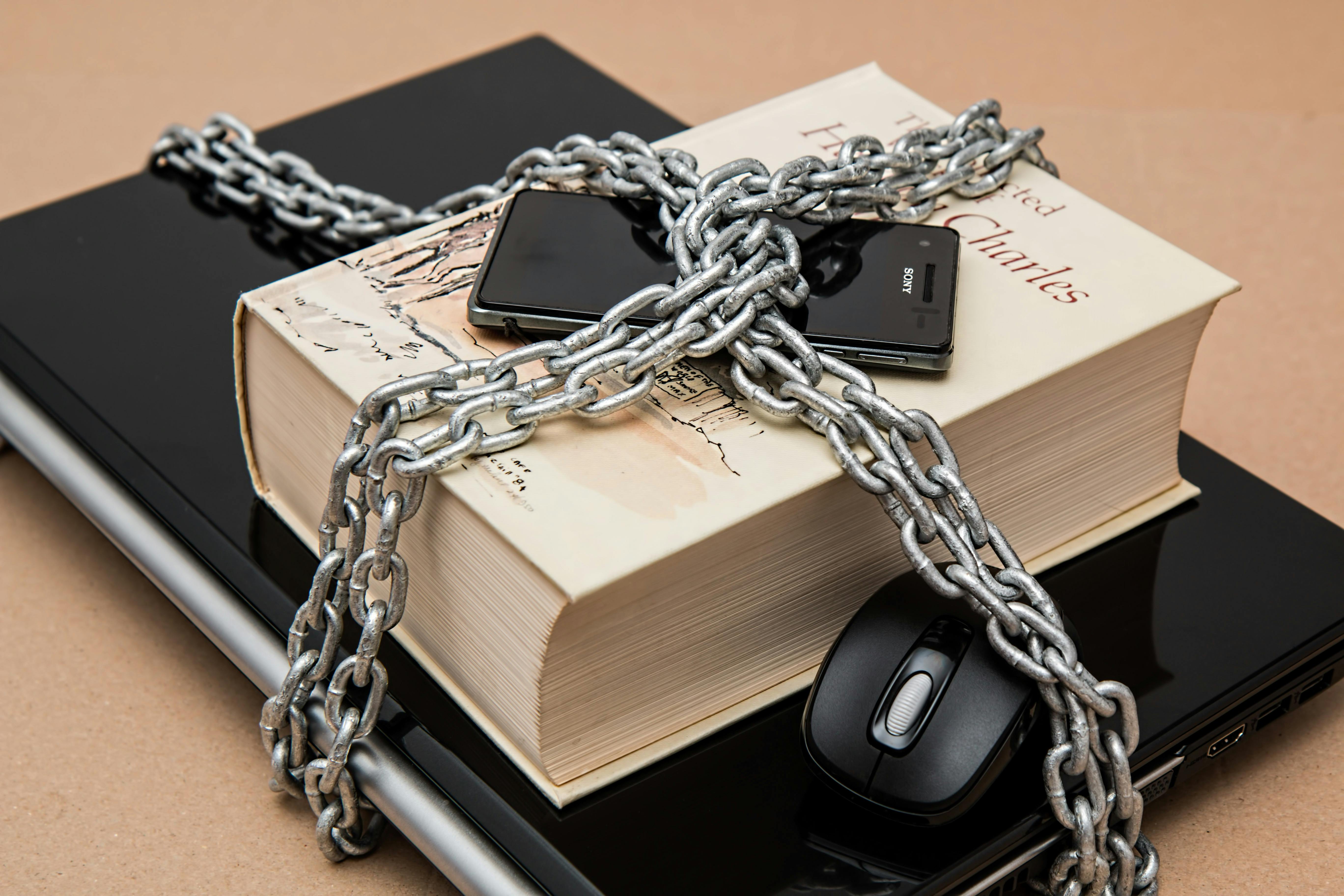
デジタル化が急速に進む現代社会において、企業におけるセキュリティ対策は経営リスクの管理そのものです。特にPCやエンドポイントデバイスに存在する「脆弱性」は、サイバー攻撃者にとって格好の侵入口であり、これを放置することは深刻なインシデントに直結します。
本記事では、なぜPC脆弱性のモニタリングが必要なのか、どのように効率的に行うべきか、そしてEXOセキュリティの導入によって得られる実効的なメリットについて解説します。
IPA(情報処理推進機構)によると、2023年に報告されたソフトウェアの脆弱性件数は10,000件を超え、前年よりも増加傾向にあります。その多くはWindows OSやブラウザ、Adobe製品など、業務用PCで利用されている主要ソフトウェアに関わるものであり、まさにPCそのものがリスクの温床となっています。
攻撃者はセキュリティ対策が不十分な中小企業を「低コスト高効率」で狙う傾向があります。特にゼロデイ脆弱性(パッチ未公開の未知の脆弱性)や、公開から数ヶ月放置された古い脆弱性がその標的になります。
2024年にJPCERTが公表した「サイバーインシデント報告件数」によると、中小企業関連の報告件数は全体の42.8%を占めています。
OSやアプリケーションごとにベンダーから出される脆弱性情報(CVE)を人手で収集・分析・パッチ適用することは、IT部門の大きな負担となります。また、手動では漏れや遅延が生じやすく、結果として脅威にさらされる期間が延びてしまいます。
以下の要件を満たす自動化ツールの導入が推奨されます:
*リアルタイム脆弱性スキャン
エージェントまたはエージェントレスで常時監視
*脆弱性DBとの連携
NVD、JPCERT/CCなどの最新情報と自動照合
*リスク優先度に基づく可視化
CVSSスコアや攻撃コード公開状況で優先順位をつけて表示
*パッチ適用自動化
管理者の許可により段階的・計画的に自動アップデート
EXOセキュリティは、クラウド型の統合エンドポイントセキュリティプラットフォームであり、以下のような脆弱性管理の全サイクルに対応しています。
PCにインストールされたOS、ブラウザ、Office、PDFリーダーなどのアプリを自動でスキャンし、既知のCVEとの突合をリアルタイムで行います。
脆弱性のCVSSスコア、既知の攻撃事例、公開からの経過時間などをもとに「緊急度」ごとに分類。管理コンソールでは視覚的にリスクがハイライトされます。
脆弱性が検知されたソフトウェアについて、利用者に通知の上で、ワンクリックでパッチを適用可能。IT管理者の一元管理も可能です。
月次・週次で自動生成されるレポートにより、社内のセキュリティ委員会や監査対応にも柔軟に対応。ISMSやSOC2の要件にも準拠可能です。
|
メリット |
内容 |
|---|---|
|
管理の効率化 |
手動による情報収集・更新の負担を大幅軽減 |
|
リスクの可視化 |
部門別・端末別に脆弱性の一覧が一目でわかる |
|
セキュリティ強化 |
攻撃を受ける前に、弱点を塞ぐ予防的セキュリティ |
|
監査対応の強化 |
コンプライアンス要件(ISMS、NISC指針)に対応しやすくなる |
|
コスト最適化 |
被害コスト(データ復旧・信頼回復)のリスクを大幅削減 |
PC脆弱性の管理は、もはや「やるか・やらないか」ではなく「どう効率的にやるか」が問われる時代です。中小企業であっても、最低限の脆弱性対策を講じることは事業継続の前提条件であり、EXOセキュリティのような統合プラットフォームを活用することで、人的リソースが限られていても高水準なセキュリティ運用が可能になります。
「守るべき情報」を守るために、まずは足元のPCから安全を確保していきましょう。