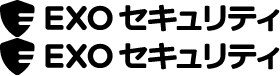


生成AIの進化により、業務効率化やアイデア創出といった多くのメリットが企業にもたらされています。
なかでもChatGPTなどの対話型AIは、誰でも簡単に使える利便性から、ビジネスの現場に急速に浸透しつつあります。しかしその一方で、利便性の裏には情報漏えいや不正利用といったセキュリティ上の重大なリスクも潜んでいます。
本記事では、生成AI活用にともなうリスクの実態と、企業が取るべき対策について解説します。
1.生成AI活用が企業にもたらす変化
生成AIは今、企業の業務改革に大きな影響を与えています。単なる便利なツールにとどまらず、組織の生産性や競争力を左右する存在となりつつあります。ここでは、企業における生成AIの導入がどのような変化をもたらしているのかを整理します。
ChatGPTをはじめとする生成AIは、自然言語による入力に対して、人間が書いたような文章や提案を瞬時に出力できる点が大きな特徴です。たとえば、社内文書や報告書の作成、議事録の要約、英文メールの作成、コードの自動生成など、多くの業務で実際に活用されています。こうした活用により、担当者の負担を大幅に軽減しながら、作業のスピードと精度を高めることが可能になります。
特に、限られた人員で多様な業務をこなす必要がある中小企業では、生成AIが業務支援ツールとして導入されるケースが増えており、その導入効果は高く評価されています。
ChatGPTは、プログラミングやシステム開発の知識が一切なくても、誰でも直感的に使える点が大きな魅力です。たとえば、「このメールの内容を丁寧な敬語に書き換えて」「プレゼンの導入文を考えて」といったように、普段使っている日本語をそのまま入力するだけで、高品質なアウトプットが得られます。
これにより、ITリテラシーにばらつきがある職場でも、導入直後から多くの社員が即戦力として活用できる環境が整います。作業にかかる時間が大幅に短縮されることに加え、内容の質にも一定の水準が保たれるため、業務の標準化にも寄与します。
生成AIは今後、単なるサポートツールを超え、人間の同僚と同様の役割を果たすようになると予想されています。たとえば、営業支援AIが商談内容を分析して提案資料を自動作成したり、カスタマーサポートAIが問い合わせ内容に応じて最適な回答を提示したりすることで、人間と協働しながら業務を遂行するようになります。
このようなAIの同僚化が進むことで、従業員は単純作業から解放され、より創造的・戦略的な業務に集中できるようになります。企業にとっては、限られた人材資源を最大限に活用するための強力な手段となるでしょう。
2.ChatGPTが情報漏えいの温床になる理由
生成AIの活用には利便性だけでなく、セキュリティリスクも伴います。とりわけChatGPTは、その利用形態から情報漏えいの危険性が高いと指摘されています。本節では、なぜChatGPTが情報漏えいの温床となりうるのか、その具体的な理由を解説します。
ChatGPTなどの生成AIは、サービスの精度向上や品質改善を目的に、ユーザーが入力した内容をAIの学習データとして再利用する場合があります。特に無料プランや制限付きのAPIでは、入力内容が匿名化されたうえでAIのトレーニングデータに活用されることが、利用規約上で明記されていることも珍しくありません。
企業の従業員が業務中にAIに入力した文章、たとえば、未公開の製品情報や契約書のドラフトなどが、後に第三者のAI利用において再生成されてしまう事態も理論的には起こり得ます。このような仕組みを理解せずに機密性の高い情報を入力すると、意図せず企業の知的財産が漏えいするリスクが生じます。
ChatGPTは直感的に利用できる一方で、入力内容がクラウド上で処理されるという認識が十分に浸透していない場合、従業員が不用意に機密情報を入力してしまうことがあります。たとえば、「顧客Aとのやり取りを要約して」「この売上データをグラフにして」などといった入力の中に、顧客データや社外秘情報が含まれてしまうケースが考えられます。
このような情報がAIシステム上に蓄積された場合、今後の学習や出力内容に影響を与え、他のユーザーが似たような質問をした際に、意図せず再利用される可能性も否定できません。情報の断片的な入力が蓄積されることで、より深刻な漏えいにつながるリスクがあることを、企業は十分に認識しておく必要があります。
ChatGPTは、Webブラウザさえあれば誰でもすぐに使い始めることができるため、社内でルールが整備されていない状態でも個々の判断で利用されがちです。とくに中小企業やITガバナンスが未整備な組織では、こうした生成AIツールの勝手利用が横行しやすく、いわゆるシャドーIT(組織が把握・管理していないIT利用)の温床となっています。
管理者の目が届かないところで、個人が自由に生成AIを活用すれば、知らぬ間に機密情報が外部に流出するリスクが高まります。また、利用実態の把握が困難なため、問題発生時に原因を特定しづらく、再発防止策の構築にも時間を要することが多い点も課題です。
生成AIの恩恵を受けるためには、企業としてセキュリティリスクに正しく向き合い、具体的な対策を講じる必要があります。本節では、企業が講じるべき基本的な対策と管理体制の整備について詳しく紹介します。
まず重要なのは、生成AIの利用に関する明確な社内ルールを整備することです。「どのような用途で使用してよいか」「入力してはならない情報とは何か」といった具体的な方針を文書化し、従業員に周知することが求められます。
たとえば、顧客の氏名や住所といった個人情報や、契約書や財務データ、開発中の製品情報といった機密情報などの入力は禁止すべきでしょう。禁止事項を具体的に明示することで、従業員の認識不足による誤使用を防ぐ効果が期待できます。
ChatGPTを利用する場合でも、社内専用のセキュアな環境で利用できる有料版やAPIの活用を検討することで、外部への情報流出リスクを最小限に抑えることが可能です。一部の企業では、社内で生成AIを独自に構築したり、信頼できるベンダーとの提携によりセキュリティ対策済みのAI環境を整備したりする取り組みも進んでいます。オープンなAIサービスの使用を一律に禁止するのではなく、信頼性の高い利用手段を提供することで、利便性と安全性のバランスを取ることが可能になります。
生成AIのリスクを正しく理解し、安全に活用できる人材を育成するためには、社内教育が欠かせません。特に、IT部門以外の一般社員に対しては、「どのような使い方が危険か」「誤入力がどんな影響を及ぼすか」といった基本的な知識の習得が重要です。
eラーニングや集合研修、ハンドブックの配布などを通じて、セキュリティリテラシーを継続的に高める仕組みを整えることが、事故の未然防止につながります。
誰が、いつ、どのような目的で生成AIを利用したのかを記録・可視化することは、セキュリティ対策として極めて有効です。仮に情報漏えいなどのインシデントが発生した場合でも、ログデータをもとに状況を特定し、迅速な対応を行うことが可能になります。
AI活用を組織的に管理するには、利用履歴を収集・分析できる監視ツールや専用のプラットフォームを導入することも検討すべきでしょう。
生成AIは進化が著しく、新たな機能や仕様変更にともなって新たなリスクが発生する可能性があります。そのため、導入時だけでなく、継続的な運用中にも情報システム部門がモニタリングを行い、リスクの変化に応じた見直しを実施することが求められます。
セキュリティ監査や内部レビューを定期的に実施し、ルールやツールの更新、教育内容の再構成など柔軟に対応できる体制を構築しておくことが、長期的な安全運用の鍵となります。
生成AIを安全に活用するには、外部サービスの利用方法にも注意が必要です。提供元の契約内容や規制との整合性を理解し、自社のデータを守るための基準を明確にしておくことが重要です。
AIサービスを利用する前に、提供元が公開している利用規約やプライバシーポリシーを必ず確認しましょう。
特に注視すべきは以下の点です。
・ユーザーの入力情報が保存されるか
・入力データが学習目的に使われるか
・第三者に情報が提供される可能性があるか
たとえば、あるサービスでは有料版のみが「データの非学習化」に対応しているなど、プランによって扱いが異なる場合もあります。こうした仕様を事前に把握し、自社のセキュリティポリシーと照らし合わせて判断することが大切です。
外部の生成AIサービスが海外ベンダーによって提供されている場合、各国のデータ保護法との整合性も確認が必要です。たとえば、EUのGDPR(一般データ保護規則)では、個人データの取り扱いに関する厳格な規定があり、違反した場合は高額な罰金が科される可能性もあります。
日本企業であっても、海外の顧客情報を扱っている場合や、海外サービスを経由してデータを処理する場合には、これらの規制が適用されることがあります。利用前には法務部門とも連携し、契約条件のリスク分析を行うことが望まれます。
生成AIを活用するにあたり、社内の情報を社外のAIサービスに入力することは、形式上「情報の社外持ち出し」に該当します。そのため、これを許可する範囲や条件について、明確なルールを定めておくことが必要です。これにより、生成AIを利用する環境や状況に応じて、情報漏えいのリスクを最小限に抑えることができます。
まとめ
生成AIは業務効率化や創造性の拡張といった大きな可能性を秘めていますが、その利便性の裏には重大なセキュリティリスクが潜んでいます。とくにChatGPTのような外部AIツールは、情報漏えいのリスクが企業の管理下を超えて広がる恐れがあり、軽視すべきではありません。
企業としては、生成AIの利活用を進める一方で、明確な利用ルールの策定、社員教育、技術的な統制措置を通じて、安全かつ効果的な活用環境を整備することが求められます。
今後ますます普及が見込まれる生成AIとどう向き合うかが、企業の信頼性と競争力を左右する重要な鍵となるでしょう。