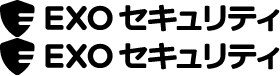

コロナ禍をきっかけに急速に普及したテレワークは、今や多くの企業で定着しつつあります。
しかしその一方で、従来のオフィス中心の働き方を前提としたセキュリティ体制では、対応しきれない課題も浮き彫りになっています。社外からのアクセスや私物端末の利用など、リスクが多様化する中で、企業は改めてセキュリティポリシーの見直しを迫られています。
本記事では、テレワーク時代に必要なセキュリティの再構築に向け、現状のリスクと見直しのポイント、そして企業が取るべき具体的な対策をわかりやすく解説します。
テレワークは利便性や生産性の向上をもたらす一方で、従来の社内ネットワーク中心のセキュリティモデルでは防ぎきれない脅威が増加しています。ここでは、その背景とリスク要因を整理します。
テレワークの広がりに伴い、VPN機器やリモートデスクトップを狙ったサイバー攻撃が急増しています。攻撃者は、社外からのアクセスが増えた企業ネットワークの脆弱性を突き、情報窃取や不正侵入を試みます。特に、中小企業では十分なセキュリティ対策が整っていないケースも多く、標的型攻撃の被害が拡大しています。
また、攻撃の手口も巧妙化しており、フィッシングメールやマルウェア感染による情報漏えいなど、人の不注意を突く攻撃も後を絶ちません。
テレワーク環境では、家庭内のWi-Fiルーターや私物パソコンなど、企業が直接管理できないデバイスが業務に利用されることがあります。これらの機器はセキュリティ更新が不十分であったり、初期設定のまま使われていたりすることが多く、外部からの侵入リスクを高める要因となります。
特に、私物端末の業務利用( BYOD:Bring Your Own Device)が広がる中で、企業データと個人データが混在し、情報管理の線引きが曖昧になるケースも増えています。
テレワークでは、上司や同僚との対面での確認が難しく、誤送信や共有ミスによる情報漏えいが発生しやすい環境です。さらに、家庭内での会話や資料の取り扱いが第三者の目に触れる可能性もあり、オフィスでは想定されなかったリスクが潜んでいます。
このように、テレワークの普及によって、技術的なセキュリティだけでなく、人の行動に起因するリスク管理もより一層重要になっています。
こうした新たなリスクに対応するためには、社内ネットワーク内なら安全という前提を捨て、場所やデバイスに依存しないセキュリティ体制を構築することが求められます。そのためには、既存のセキュリティポリシーを根本から見直し、新しい働き方に対応したルールと仕組みを整備する必要があります。
以下では、その際に重点的に確認すべき主要なポイントを解説します。
まず見直すべきは、アクセス管理の仕組みです。IDとパスワードだけに頼る認証では不正アクセスを防ぎきれません。多要素認証(MFA:Multi-Factor Authentication)の導入により、ログイン時のパスワードに加えてワンタイムパスコード、生体認証(指紋・顔認証など)、または認証アプリを使用することで、本人確認の精度を大幅に高めることができます。
また、近年注目されているのが ゼロトラストセキュリティモデルという考え方で、「全てのアクセスを信頼しない」という原則に基づいたものです。従業員がどこからアクセスしても、通信の暗号化・端末の安全性チェック・利用状況のモニタリングなどを組み合わせ、動的にアクセス制御を行うことで、安全な業務環境を維持できます。
次に重要なのが、業務に利用されるデバイスをどのように管理するかという体制の整備です。
テレワークでは、会社支給のノートPCだけでなく、個人所有のスマートフォンやタブレットが利用されるケースも増えています。こうした多様な端末が社内ネットワークやクラウドに接続することで、管理が煩雑になり、セキュリティリスクが高まるのです。
この課題を解決するためには、デバイス管理ポリシーの明確化が不可欠です。企業は、利用可能な端末の種類・OS・ソフトウェアのバージョン・セキュリティ設定などをルール化し、遵守を徹底させる必要があります。
また、モバイルデバイス管理 (MDM:Mobile Device Management)の導入により、端末の状態監視や、紛失・盗難時のリモートワイプ(データ削除)機能、アプリ利用制限などを行うことで、情報漏えいリスクを大幅に軽減できます。
さらにBYODを認める場合は、業務データと個人データを明確に分離する仕組みを導入することも重要です。例えば、業務アプリを企業専用のコンテナ領域内で動作させ、個人領域とはデータが交わらないように設定することで、従業員のプライバシーを守りながら企業情報を安全に管理できます。
テレワークでは、従業員がオフィス外でデータを扱う機会が増えるため、情報の持ち出しや保存に関するルール整備が欠かせません。もしUSBメモリや外付けハードディスクに業務データを保存し、それが紛失・盗難に遭えば、重大な情報漏えいにつながる恐れがあります。こうしたリスクを防ぐためには、特に、物理的なデータ持ち出しを制限し、必要に応じて暗号化を義務付けることが重要です。
また、業務データはできる限りクラウドストレージや社内のファイルサーバーで一元管理し、アクセス権限を明確に設定することで、データの所在と利用履歴を追跡できるようにします。
さらに、個人情報や機密資料など、データの機密度に応じた取扱基準を定め、誰が・どのデータを・どの環境で扱えるかを明文化することが求められます。定期的な社員教育やチェック体制を整備し、従業員全体で同じ意識と行動ルールを共有することが、情報漏えい防止の第一歩です。
テレワークで頻繁に利用される通信・クラウド環境の安全性についても、見直しが必要です。ZoomやMicrosoft Teamsなどのオンライン会議ツール、Google DriveやBoxなどのクラウドストレージは便利な一方で、設定不備やアクセス権の管理ミスが原因で情報漏えいが発生する事例も少なくありません。
そのため、利用するサービスを選定する際には、暗号化通信(TLS)への対応状況、データ保管場所、アクセス権限の詳細設定が可能かどうかを基準に検討する必要があります。クラウド上でデータを扱う際は、多層的なセキュリティを施すことが基本です。
例えば、アクセスログの自動記録やIPアドレス制限、不審なアクセス検知などを組み合わせることで、外部からの侵入や内部不正を防ぐことができます。また、従業員が無断で業務外のクラウドサービスを使用する「シャドーIT」を防ぐためにも、利用可能なクラウドサービスの一覧や承認プロセスを明確化することが大切です。
これにより、組織全体で統一されたルールのもと、安全かつ効率的にクラウド活用を進めることができます。
セキュリティポリシーの見直しを効果的に進めるためには、実践的な対策を組み合わせて運用することが不可欠です。ここでは、企業がすぐに着手できる5つの施策を紹介します。
テレワークの普及により、従来の「社内ネットワークは安全」という前提は崩れつつあります。社外からのアクセスが増えたことで、通信経路の安全性がこれまで以上に重要になりました。
まずは、VPNを活用して安全な通信経路を確保することが基本です。これにより、従業員が自宅や外出先から社内システムへアクセスする際も、第三者による盗聴や改ざんを防げます。さらに、ゼロトラストセキュリティの考え方を前提に、アクセスするたびに認証・検証を行う仕組みを導入することで、社内外を問わず一貫したセキュリティ基準を維持し、内部不正や侵入後の被害拡大も防止します。
通信経路を守るだけでは不十分です。攻撃者はしばしば、従業員の端末(エンドポイント)を突破口として侵入します。このような攻撃から企業を守るためには、エンドポイントセキュリティの強化が不可欠となります。
エンドポイントセキュリティの中心となるのが、EPP(Endpoint Protection Platform)とEDR(Endpoint Detection and Response)です。
EPPは、ウイルス対策ソフトの進化版ともいえる存在で、マルウェアやスパイウェアの侵入を事前に防ぐことを目的としています。既知の脅威をシグネチャやAIによるパターン分析で検知し、感染を未然に防止します。
一方、EDRは、EPPで防ぎきれなかった未知の脅威に対応するための仕組みであり、端末上の挙動を常時監視し、不審な行動を検知・隔離・調査します。攻撃を検知して対処することに特化しており、万一侵入を許しても被害の拡大を最小限に抑えることが可能です。
これらに加えて、MDMによるデバイス管理も重要です。紛失・盗難時のリモートロックやデータ削除機能を活用することで、情報漏えいリスクを大幅に低減できます。
EPP、EDR、MDMなどを組み合わせて運用することで、従業員の働く環境を守りながら、企業データの安全を確保できます。
クラウドサービスの利便性は高い一方で、管理の甘さが情報流出の原因になるケースも少なくありません。特にシャドーITは、企業のセキュリティを大きく脅かす要因です。
まずは、社内で利用されているクラウドサービスを洗い出し、誰が・どのサービスを・どのように利用しているかを明確にしましょう。
その上で、従業員ごとに必要最低限のアクセス権限を設定します。これにより、情報への不正アクセスや誤操作による漏えいを防ぐことができます。また、CASB(Cloud Access Security Broker)などのツールを活用すれば、クラウド利用状況の可視化やアクセス制御を自動化し、運用負担の軽減にもつながります。
どれほど高度なセキュリティ対策を導入しても、最終的なリスクは人から発生することが多いのが現実です。フィッシングメールの添付ファイルを不用意に開く、怪しいリンクをクリックする―こうした行動ひとつで、システム全体が危険にさらされることになります。
そのためにも、定期的なセキュリティ教育と意識啓発が大切です。社内研修や、模擬攻撃(フィッシング訓練)を通じて、従業員が自ら危険を判断し、適切に行動できるようにすることが求められます。セキュリティ違反が発生した場合の報告体制を整備し、ミスを隠さない文化を醸成しましょう。これにより、早期発見・早期対応のサイクルが組織内に定着します。
教育によって従業員一人ひとりの意識を高めることができても、実際の被害発生時に冷静に対応できる体制がなければ十分とはいえません。そこで重要になるのが、次の「インシデント対応体制」の整備です。
どれほど堅牢な防御策を講じても、リスクを完全にゼロにすることは不可能です。そのため、被害が発生した際にどれだけ迅速に対応できるかが、企業の信頼を左右します。
まずは、インシデント対応の手順を明文化し、誰が・何を・どの順に行うかを明確に定めましょう。これにより、混乱を最小限に抑えた初動対応が可能になります。さらに、実際の攻撃シナリオを想定したインシデントレスポンス訓練を定期的に実施することで、組織全体の対応力を高められます。
被害の拡大を防ぐためには、社内だけでなく、外部の専門機関やセキュリティベンダーとの連携体制の構築も欠かせません。実践的な訓練と協力関係の確立が、最終的な防波堤となります。
テレワークは今後も継続的に活用される働き方として定着していくと考えられます。企業に求められるのは、利便性とセキュリティを両立させた、バランスの取れた運用体制の構築です。そのためには、一度策定したポリシーを固定化せず、環境の変化や新たな脅威に応じて柔軟に見直していく姿勢が欠かせません。
経営層・情報システム部門・従業員が一体となり、セキュリティの継続的な改善に取り組むことが重要です。
セキュリティは導入して終わりではなく、常に更新し続けるべきものであることを意識し、持続的な取り組みを推進していきましょう。