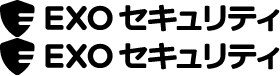

サイバー攻撃や内部不正が発生したとき、企業が真っ先に求められるのは「事実の把握」と「証拠の保全」です。特に中小企業ではセキュリティ体制が十分でない場合も多く、被害発生後の対応が企業の命運を左右することもあります。
この記事では、トラブル発生時に欠かせないデジタル・フォレンジックについて、中小企業の視点からその重要性と実践方法をわかりやすく解説します。
デジタル・フォレンジックとは聞き慣れない言葉かもしれませんが、情報セキュリティ対策において非常に重要な技術です。まずは、デジタル・フォレンジックの定義や基本的な役割、調査の対象や手法について押さえておきましょう。
デジタル・フォレンジックとは、パソコンやスマートフォン、サーバーなどの電子機器に保存されたデータを、科学的かつ法的に有効な方法で収集・分析・保全することを指します。
本来は、刑事事件などで電子的証拠を解析するために用いられてきた技術ですが、現在では企業内の不正調査やサイバー攻撃の被害解析にも広く活用されています。主な目的は、不正の証拠を正確に把握し、事実関係を明らかにすることです。
フォレンジック調査の対象となるのは、パソコン、スマートフォン、USBメモリ、各種サーバー、社内ネットワーク機器など多岐にわたります。
調査手法には、たとえば以下のようなものがあります。
・ディスクイメージの取得(原本を保護したうえで解析を行う)
・操作ログやアクセス履歴の解析
・削除済みデータの復元
・通信履歴やメール内容の調査
これらの調査結果により、いつ・誰が・どのような操作を行ったかといった情報を正確に特定することで、事実に基づいた対応や判断が可能となります。
デジタル・フォレンジックは、サイバー攻撃による被害原因の特定、情報漏えい経路の調査、そして内部不正の証拠収集などに不可欠な技術です。
近年では、企業が被害を受けた後に対応を誤ったことによって、被害が拡大したり、社会的信用を大きく損なったりする事例も少なくありません。正確な調査と適切な証拠保全が、企業の信頼維持と再発防止のカギを握ります。
「うちは小さな会社だから、サイバー攻撃や不正のリスクは低い」と考えていませんか?実は、近年のセキュリティ被害の傾向を見ると、中小企業こそが標的にされやすくなっています。ここでは、なぜ中小企業にこそデジタル・フォレンジックの備えが必要なのか、その理由を具体的に解説します。
「セキュリティ対策は大企業の課題」と考える企業は少なくありません。しかし実際には、セキュリティ体制が手薄な中小企業こそが、攻撃者にとって狙いやすい標的になっているのです。
また、取引先である大企業への侵入経路として、中小企業が踏み台にされるケースも増えています。こうした背景から、今やサイバー攻撃は規模に関係なく、サプライチェーン全体のリスクとして認識される時代になっているのです。
中小企業では、少人数で多くの業務を兼任することが一般的であり、その結果、内部の監視体制が甘くなる傾向があります。そのため、従業員による不正アクセスや、退職時の営業データ・顧客情報の持ち出しといったトラブルが起きやすいのです。
このようなケースでは、「何が起きたのか」「誰が関与していたのか」を正確に把握する必要があり、デジタル・フォレンジックによる証拠分析が欠かせません。
不正や攻撃が発覚した後、証拠が残っていなければ、原因や責任の所在を明らかにすることが難しくなります。その結果、再発防止策が不十分となり、同じトラブルが繰り返される可能性も否定できません。さらに、被害者や取引先からの訴訟・損害賠償リスクに発展するおそれもあり、「証拠があるかどうか」が企業の信頼や将来を左右する重大な要因となります。
実際にトラブルが発生した際、どのような対応を取るかによって、その後の被害の拡大や信頼の損失に大きな差が出ます。ここでは、不正発覚後に取るべき初動対応を、3つのステップに分けてわかりやすく説明します。
トラブル発覚後にまず行うべきは、関連する機器やデータの保全です。誤って電源を切ったり、ファイルを開いたりすると、重要な証拠が上書きされる可能性があります。パソコンやサーバーの操作は最小限にとどめ、可能であれば外部の専門家に証拠保全を依頼するのが望ましい対応といえるでしょう。
証拠が確保できたら、アクセスログや操作履歴、ネットワーク通信記録などをもとに不正の経緯や手口を特定していきます。この過程で、誰が・いつ・どのような方法で不正行為を行ったかを明らかにすることが求められます。フォレンジック調査では、調査の客観性と証拠能力が極めて重要です。
情報漏えいや不正が判明した場合は、社内関係者(経営陣、総務、法務など)への速やかな共有とともに、必要に応じて顧客や関係機関(個人情報保護委員会など)への報告も検討が必要です。報告内容は、事実に基づき正確で誠実でなければなりません。曖昧な説明や隠ぺいは、さらなる信頼低下を招く恐れがあります。
デジタル・フォレンジックは高度な専門知識と技術を要するため、多くの中小企業では社内だけでの対応が難しいのが実情です。ここでは、信頼できる外部業者の選び方や、依頼前に準備しておくべきポイントについてわかりやすく解説します。
デジタル・フォレンジックは高度な専門性を要するため、多くの中小企業では外部の専門業者に依頼するのが一般的です。
専門業者に依頼する際は、以下の点を確認するといいでしょう。
・実績と信頼性
:過去の対応事例や実績がどの程度あるのか確認しましょう。官公庁や大手企業への対応経験がある業者は、信頼性が高い傾向にあります。
・法的な証拠能力
:収集した証拠が法的に有効と認められるかを、意識した調査手法を採用しているかを確認してください。
・情報管理体制
:機密情報を扱うため、厳格な守秘義務体制が整っているかも重要なチェックポイントです。
費用は案件の規模や調査範囲によって異なりますが、小規模な調査でも数十万円〜、大規模案件では数百万円以上かかることがあります。調査期間は、初動対応を含めて数日〜数週間程度が一般的です。
なお、予算に限りがある場合は、調査の対象となる端末や期間、調査目的を絞ることで、費用を抑えることが可能です。たとえば、特定のパソコンやメールアカウントに限定して調査を行ったり、発覚時期の前後に絞ってログを解析したりすることで、必要最低限の範囲にとどめながらも効果的な対応が図れます。
・対象となる機器やデータの一覧
・トラブルの概要と発覚経緯
・社内での連絡体制(対応窓口や責任者の明確化)
これらを準備しておくことで、調査の精度が高まり、対応にかかる時間やコストを抑えることができます。
中小企業にとっても、サイバー攻撃や内部不正といった情報セキュリティの脅威は、決して他人事ではありません。
万が一の際に備え、デジタル・フォレンジックという証拠調査の手段を理解し、初動対応や外部業者との連携体制を整えておくことが、企業を守る大きな力になります。
トラブルが起きてから慌てるのではなく、いざという時に備えておく姿勢こそが、現代の中小企業に求められる情報リスク管理の第一歩です。